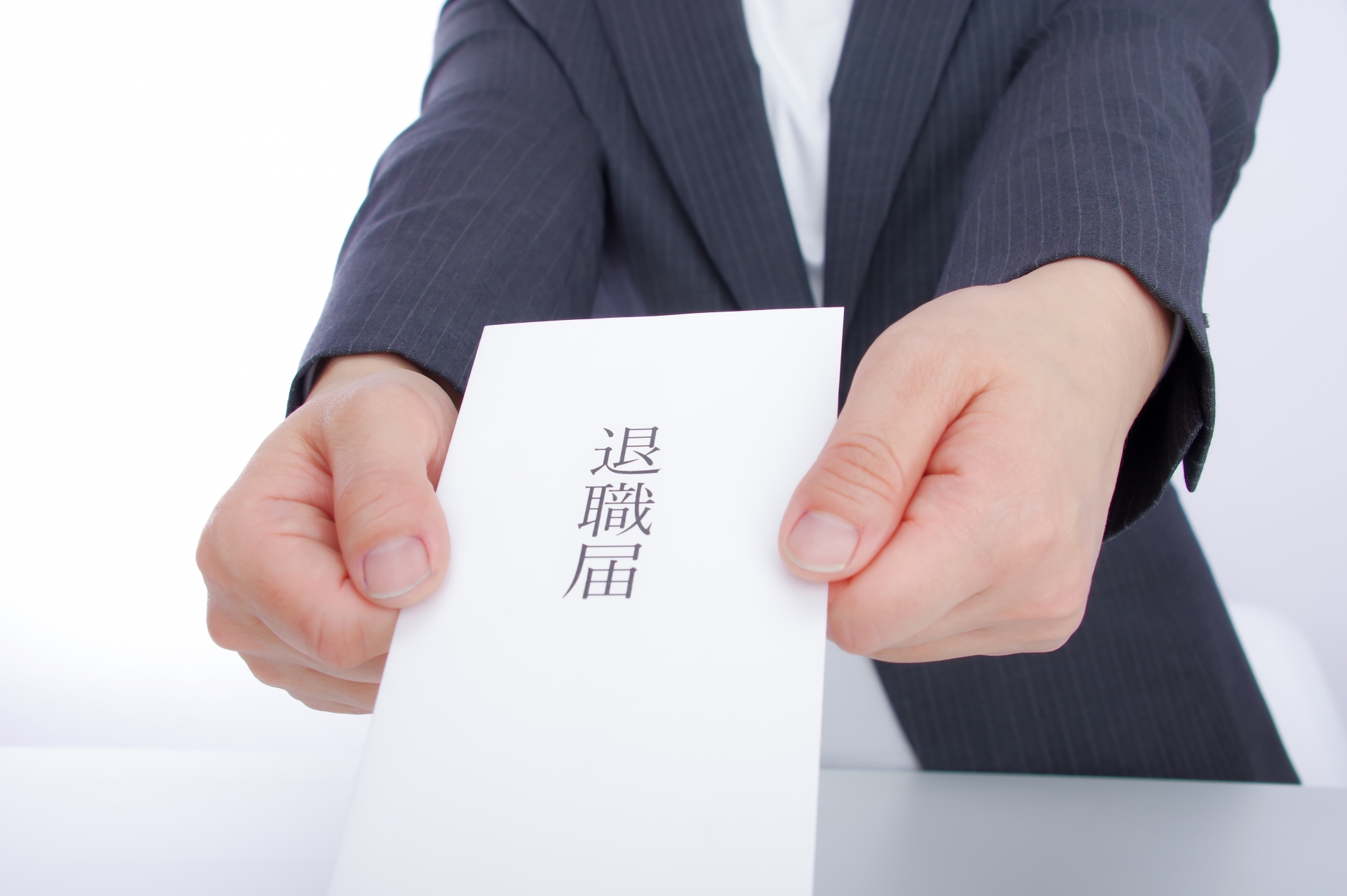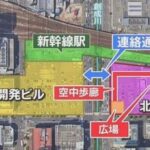こんにちは!北の熱い講師オッケーです!
10月1日に、来年度の新入社員の内定式を行った企業が多いと思います。
会社の中心軸が揺らぐ
同時に、潜んでいるのが、中堅社員の離職です。
企業にとって大きなダメージにつながりかねない中堅層の離職を防ぐには、ウェルビーイングを考える必要があります。
ウェルビーイングとは
ウェルビーイング(Well-being)とは、「よい状態」を意味し、身体的、精神的、社会的に満たされた幸福な状態を指す概念です。
この言葉は、well(よい)とbeing(状態)から成り立っており、単なる病気ではない状態や一時的な幸福感(ハピネス)とは異なり、持続的な良好な状態を意味します。
企業における重要性
従業員のウェルビーイングが向上すると、働く意欲や生産性が高まり、組織内の人間関係改善、離職率の低下、採用力の向上など、企業にとって多くのメリットがあります。
今時の退職傾向とは
Z世代の新人、若手の人たちが入社後、時間がたたないうちに辞めていくことや自らそれを申告・届け出をせず、退職手続きの代行業者に委託する形で退職していくことが話題になっています。
このような傾向は特に令和時代の特徴というわけではなく、四半世紀ほど前から、入社後3年以内に中学卒業の7割、高校卒業の5割、大学卒業の3割が辞めるという「7:5:3」という言い回しで職場関係者に浸透してきました。
厚生労働省が2024年10月に公表した調査では、入社後3年以内の離職率が、中卒は50.5%、高卒が38.4%、短大等の卒業が44.6%、大卒では34.9%となっています。
職場環境の悪化
新人や若手の唐突な離職は、少なからず精神的なダメージを上司・先輩に与えます。
ところが近年、中堅と目される会社の担い手の人たちが突然、離職してしまうケースが目立ってきました。
転職支援サービスの進展で即戦力というキャッチフレーズのもと、テレビやネットのコマーシャルで転職が中堅層の注目を集めている影響もあると思います。
職場内で重要な役割を担っており、会社の将来を任せたいと考えていた中堅層の離職は心理的な面だけでなく、業績に影響を及ぼす物理的なインパクトが大きいです。
未来の職場の存続を脅かしかねないのが中堅層の離職です。
見えない中堅の離職理由とは

皆さんは中堅社員が離職するかもしれないことを日頃から、意識しているでしょうか。
もしもそうしたことが起きた場合にどのような理由があると思いますか?
厚生労働省の調査では前職を辞めた理由が示されていますが、30代の男性では給料等の収入が少なかったことに続いて、
職場の人間関係が好ましくなかったこと、労働時間、休日等の労働条件が悪かったこと、仕事の内容に興味が持てなかったことが多い理由のようです。
女性では仕事の内容に興味が持てなかったこと以外は、男性と同様の理由が多くなっています。
ただ、これらは一般的な言い回しに過ぎず、個別のケースの退職理由を正確に言い当てているわけではないと思います。
例えば、Z世代より前に義務教育を受けたゆとり世代の人たちは30代後半に差し掛かっています。
この年齢層がZ世代を見る感覚は、シニア層が中堅層を見る感覚に近い傾向があるのです。
一方で定年延長や継続雇用で上の世代が詰まっている、つまり自身の昇進やキャリアアップが望めない状況に置かれている可能性があります。
加えて、日本では年功序列の慣習が根強く残っている企業も多く、常に敬語を使い、社内だけでなく、出張や移動の最中、上司、先輩に気を使う日々を送っている人が少なくないと思います。
優秀な人材を外資系企業に採用されてしまう危機感もあって、大手企業では新卒入社の人たちに30万円を超える初任給を提示するようになりました。
30代の人たちが就職した頃とは段違いの好待遇であり、その若手の面倒を見るよう求められれば、「やっていられない」という気持ちが出てくるのも当然です。
努力に応じたご褒美が欲しいという本能?本音が存在します。
中堅クラスの社員は、社会経験があれば、離職後に転職しても、うまく適応できるかは未知数であると分かっているはずです。
それでも転職したくなる動機が形作られる背景を説明できるストレス理論として、ドイツ人社会学者のシーグリスト氏が提唱した「努力-報酬不均衡モデル」があります。
厚生労働省は「努力-報酬不均衡モデル」として「職業生活において費やす努力と、そこから得られるべき、もしくは得られることが期待される報酬がつりあわない」(高努力/低報酬)の状態をストレスフルと定義している、と説明しています。
中堅の社員はこのような努力と報酬の不均衡に苦しんでいる可能性があります。
さらにシーグリスト氏は、「オーバーコミットメント」という仕事に過度に傾注する個人の態度、行動様式をリスクとして考慮しました。
認められたいという強い要求もリスク要因ですが、強い競争心も手伝って、悪い就業環境や見合わない報酬を無理にのみ込みながら、過剰に頑張る状態になりやすいということです。
ちなみに標準的に行われてきたストレスチェックの中では「努力-報酬不均衡モデル」を直接反映した測定、結果の算出は行われません。
けれども「努力-報酬不均衡モデル」を想像させる事例を皆さんは身近で見ているかもしれませんね。
例えば、役職定年を迎えた元上司・先輩がやる気を失い、気難しく不貞腐れる様子になっていく状態です。
一見、大人げないように見えるかもしれませんが、その時点では役職を解かれるだけでなく、給与も減額されてしまっています。
過去の高い職位と報酬を得ながらバリバリと働いていた頃のパフォーマンスを上げる動機が失われたわけです。
合わせておすすめの記事👇
管理職は中堅のウェルビーイングを考える必要あり

そうした先輩の変化、新人の頃の上司だった人たちがどのように会社に扱われていくのかを10年以上間近で見てきたのが中堅層です。
今や高度情報化、DX(デジタルトランスフォーメーション)を経て、AI(人工知能)を業務で活用する時代です。
中堅層が学生時代から見てきた世界は、リーマン・ショック以降の厳しい政治経済の状況や東日本大震災、能登半島地震といった自然災害の深刻な影響、戦争、地域紛争と共に社会保障制度の暗い見通しに覆われた世界です。
皆さんの職場で活躍してきた実績がある中堅層は、それだけ他社でも市場価値が高いことを意味しています。
古くから不惑とされてきた40歳を前に、将来を考えて離職する選択肢は理解できるところかもしれません。
そうした中堅層と相対する時、彼らの将来のウェルビーイングを想像するとよいと思います。
毎日見てきた彼らの努力に見合う報酬を受け取ってきたのかを尋ねてみてもよいでしょう。
報酬には目に見える形の外発的報酬とより内面的な内発的報酬がありますが、給与、肩書などは前者にあたります。
これらは一度、受け取った瞬間からもらって当たり前のものとなり、仕事に対する不満足に影響する衛生要因となります。
他方、後者は会社や職場への愛着や、最近では人事部門だけでなく経営層の関心を集め、健康経営の面でも注目される従業員エンゲージメントを高めることにも通じます。
管理職がこの内発的報酬に着目しながら、中堅層の人たちと対話し、相互理解を深めていくことはいつでも可能であると思います。
その際、年功序列の慣習を離れて、対等な人間関係という前提に立ち、心理的、身体的、社会的なウェルビーイングの状態を聞き取り、その支援や助言を心掛けることが可能です。

コミュニケーションが重要
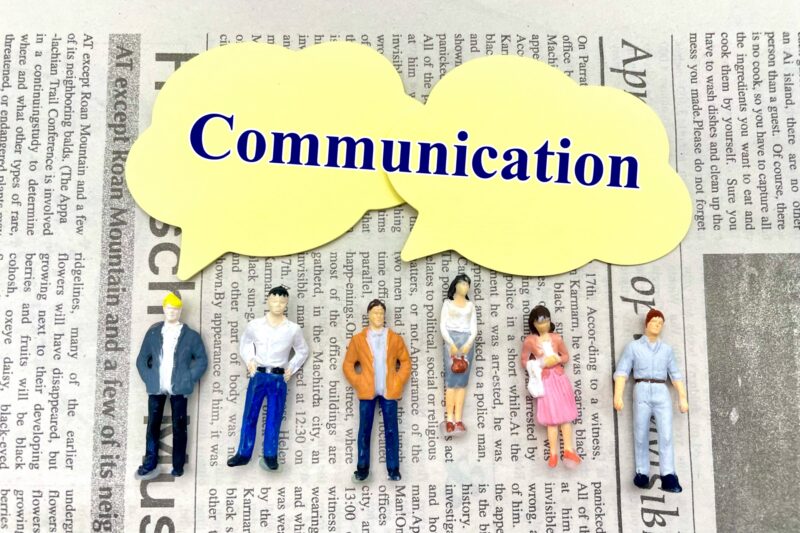
管理職の人は、過去の先輩、上司、恩師を思い浮かべて、
「あの人と会えて良かった、一緒に仕事ができて良かった」と思うことがあるでしょうか。
簡単ではないと思いますが、そうした存在になれるよう、日々、中堅層の人たちとの接点を大切にしていくことが、中堅層の人たちの離職を防ぐのにも有効ではないでしょうか。
皆さんの会社は、いかがでしょうか?
検証するは、まさしく、今でしょ!
中堅層が、退職届けを胸に秘めるが、事業年度半期過ぎた、今頃ですよ!
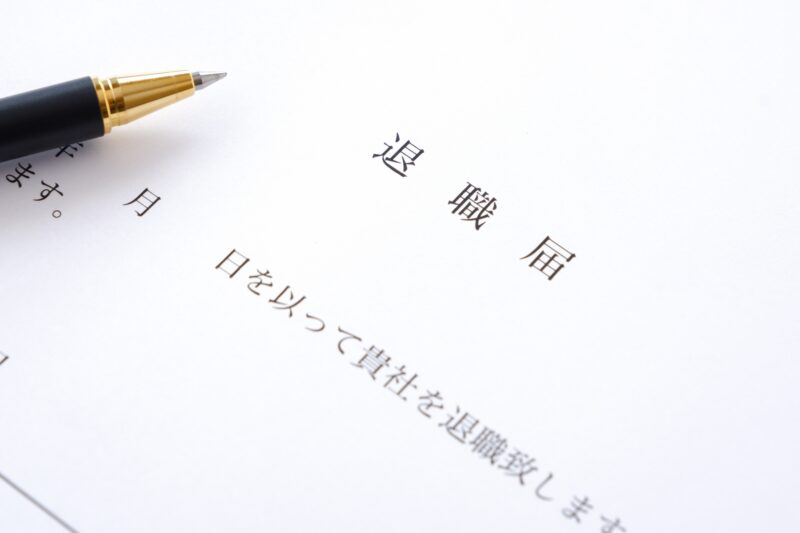
今日を大切に明るく元気に行きましょう!
お仕事の方、お疲れ様です!
いってらっしゃい!